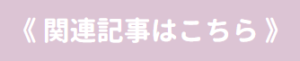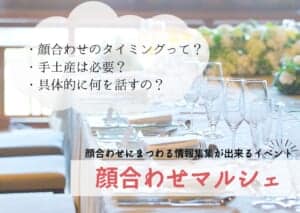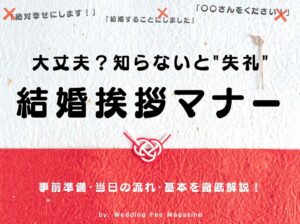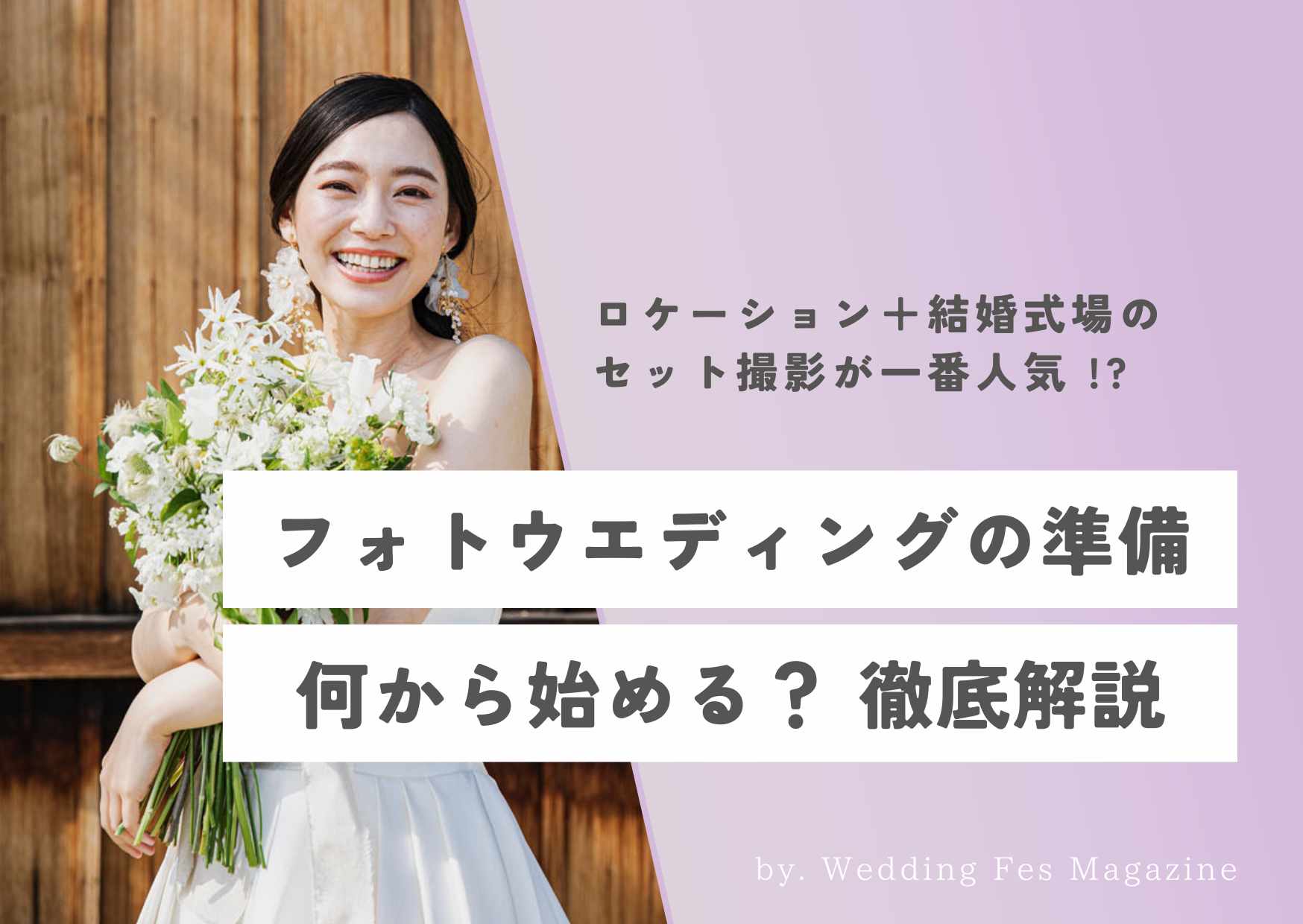『顔合わせ』は、これから結婚するふたりの両家が顔を合わせて親睦を深める食事会のことです。
最近では、結納に代わる形として行う方が増えてきました。
アットホームな雰囲気で行うケースも多いですが、お互いに手土産を交換するのが一般的です。
顔合わせは決まったルールがなく、それぞれの判断による部分が大きいので、手土産についても「これでいいの?」と不安に思う方も少なくありません。
今回は手土産に『のし』が必要かどうかを始め、基本的なマナーについて解説します!
顔合わせの手土産にのしは必要?

はじめに、『のし』にどのような意味があるのか、顔合わせの手土産に必要かどうかお伝えします!
「のし」=フォーマルな贈り物に添える飾り
『のし』とは、フォーマルな贈り物に添える飾りのことです。
本来は紙の中央右上に添えられた飾りのみを指していましたが、現在では『のし』と『水引』が印刷された『のし紙』のことを指すのが一般的となっています。
のしは慶事の贈り物の際に添える、縁起物の象徴です。
弔事の場合は、のしが付いていない水引のみの掛け紙を使用します。
のしと水引が付いているのし紙にも、祝い事の内容によってそれぞれ適した結び方や色があります。
贈る相手に失礼のないよう、おさらいしておきましょう。
のしをつけていると正式で礼儀正しい印象に
顔合わせに持っていく手土産の場合、のしは付けなくてもマナー的に問題はありません。
親睦を深めるためのカジュアルな顔合わせであれば、相手に気を遣わせないようあえて付けないこともあります。
結納の代わりとして行う、フォーマルな顔合わせ食事会の場合は、のしを付けるほうが良いでしょう。
きちっとした礼儀正しい印象になりますね♪
のしの有無は、顔合わせ食事会の会場や雰囲気、そして両家の考え方に合わせて決めるのがおすすめです。
どちらか一方だけがのしを付ける、といった行き違いでお互いに気まずくならないためにも、あらかじめ手土産についてもすり合わせておきましょう。
顔合わせの手土産につける「のし」のマナー

のしを付ける場合は、主に次の3点について注意しましょう。
<水引>
のしの中央にあるひものこと。結び方やひもの本数、色によってさまざまな意味があります。
<表書き>
水引の上に書く文字のこと。贈り物をする目的によって、記載する言葉は異なります。
<名入れ>
水引の下に書く名前のこと。贈り主の名前を記載します。
ここからは顔合わせの手土産にのしをつける際のマナーを紹介します。
水引は「紅白結び切り」を選ぶ
贈る理由が「何度あっても良い祝いごと」か「一度きりであってほしい祝いごと」なのかが水引を選ぶポイントです。
婚礼の顔合わせといったような、一度きりのお祝いでは『結び切り』を選びましょう。
何度でも結び直せる『蝶結び』の水引は、何度あっても良いお祝い、たとえば出産や入学の際に選びます。
水引の本数についても、贈る理由によって数が変わります。
縁起が良いとされている本数は奇数です。
また、結婚のご祝儀袋では10本の水引が基本マナーとなっています。
これは5本×2=10本ということから規定て、「両家が合わさる」「喜びを重ねる」などの意味を持つとされます。
顔合わせの場合、10本の水引は大げさに捉えられてしまう可能性があるため、5本か7本を選ぶのがおすすめです。
表書きには「御挨拶」もしくは「寿」と入れる
顔合わせが両家の親睦を目的としているのなら、表書きは『御挨拶』と入れましょう。
結納の代わりとして行う、ややフォーマルな顔合わせの場合は『寿』もおすすめです。
会場や両家の考え方に沿って表書きを使い分けましょう。
表書きは印刷でも問題ありませんが、毛筆や筆ペンで直接書くのもおすすめです。
色の濃い墨を使い、はっきりとした文字を書きましょう。
ボールペンで書くのはNGなので避けてくださいね。
名入れは苗字のみを書く
顔合わせは、一家を代表して挨拶をする場ですので、『家からの贈り物』として苗字を記載します。
婚礼の顔合わせの場合、手土産は一般的に両親が用意します。
ほかの親族が出席する場合も、両親以外の方の用意は不要です。
顔合わせの手土産に関するQ&A

ここからは、顔合わせの際の手土産について、多くの方が感じる疑問について解説します。
相手に喜んで受け取ってもらえるよう、ポイントを押さえておきましょう!
Q.顔合わせにおすすめな手土産の品物は?
顔合わせに持っていく手土産は、菓子折りやお酒などの食品が一般的です。
なかでも、縁起物とされる食品が人気となっています。
たとえば、バームクーヘンは大樹の年輪のような断面から、「長寿」や「子孫繁栄」という縁起の良いイメージを連想させる品物です。
また、2枚の生地であんをはさむ形状をしているどら焼きは、夫婦円満のイメージにつながる縁起物として定番の手土産です。
バームクーヘンやどら焼き以外にも縁起物といわれている食品はたくさんあります!
新しい家族の始まりにふさわしい手土産となるでしょう。
そのほかにおすすめの手土産は以下のとおりです。
・季節のフルーツ
・地酒
・地元の銘菓、特産品
・クッキー
・茶葉など
両家が遠くに住んでいる場合、地元の名産品は会話のきっかけづくりにぴったりです。
食品の場合は日持ちのするものを選ぶようにしましょう。
選択肢が多いと「何を選べばいいのかな……」と悩んでしまいますが、なにより相手の好みに合わせた手土産を選ぶことが大切です。
顔合わせの手土産について、詳しい情報は以下の記事で解説しています。
手土産選びの際に参考にしてみてくださいね。
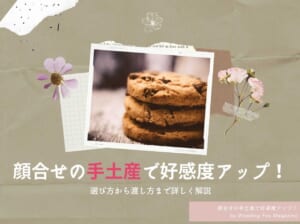
顔合わせの手土産で好感度アップ!選び方から渡し方まで詳しく解説
Q.手土産の正しい渡し方は?
手土産を渡すのは、両家がそろい、お互いの紹介や挨拶が終わったタイミングが良いでしょう。
気が焦るあまり、玄関先で渡さないように注意してくださいね。
とはいえ、傷みやすいものやアイスなどの冷凍ものは例外です。
何を持ってきたのかを伝え、冷蔵庫や冷凍庫にしまってもらえるようお願いしましょう。
また、袋(風呂敷)に入ったまま渡すのはNGです。
袋(風呂敷)には、ホコリをよけるという意味合いがあるからです。
必ず先に袋から出し、相手の正面から両手で手渡ししましょう。
その際に、「お口に合うとうれしいのですが」「お好きと伺ったので」など、心遣いのある言葉を一言添えると丁寧な渡し方になります。
よく耳にする言葉「つまらないものですが」は、顔合わせの場では避けるほうが無難です。
へりくだった言葉を好まない方もいるほか、いらぬ誤解を招く可能性があります。
渡し方によっても印象が変わってきますので、細かな部分にも配慮しましょう。
Q.手土産を持っていくときはお店の手提げ袋でもいいの?
手土産を入れるのは、品物を買ったお店の手提げ袋でも問題ありません。
しかし、もう少し特別感を演出したい場合は風呂敷を使うのもおすすめです。
風呂敷のメリットは、手土産の形状に関わらず包める扱いやすさと、真心のこもった見た目に仕上がる美しさにあります。
基本の結び方である『真結び』をはじめ、多くの包み方ができますよ。
・平包み:結ばずに織り込む、格式高い包み方
・おつかい包み:しっかりと品物を守る包み方
・瓶包み:持ち手を作れる、お酒にぴったりの包み方
・手提げかご包み:かごごとくるむ、フルーツ盛りにおすすめの包み方
色合いや柄がかわいらしい風呂敷なら、その場の雰囲気も明るくしてくれます!
風呂敷は素材や柄のバリエーションが豊富なので、事前に購入し、包む練習をしておくと良いでしょう。
顔合わせ当日は、風呂敷から出すタイミングやしまうときにも手間取らないよう注意し、スマートに手土産を渡しましょう。
まとめ
品物選びから包み方、渡し方にいたるまで、顔合わせについて疑問に思うことはたくさんあるかと思います。
「もう少し詳しく聞きたい」「こんな場合はどうするの?」といった不安のある方は、顔合わせの進行・準備について聞ける総合イベント『顔合わせマルシェ』に参加してみませんか?
手土産についてはもちろん、そのほかの細かなことの相談や体験サービスを提供しています。
顔合わせについて不安を解消したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
今回はここまで!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!