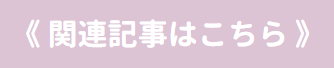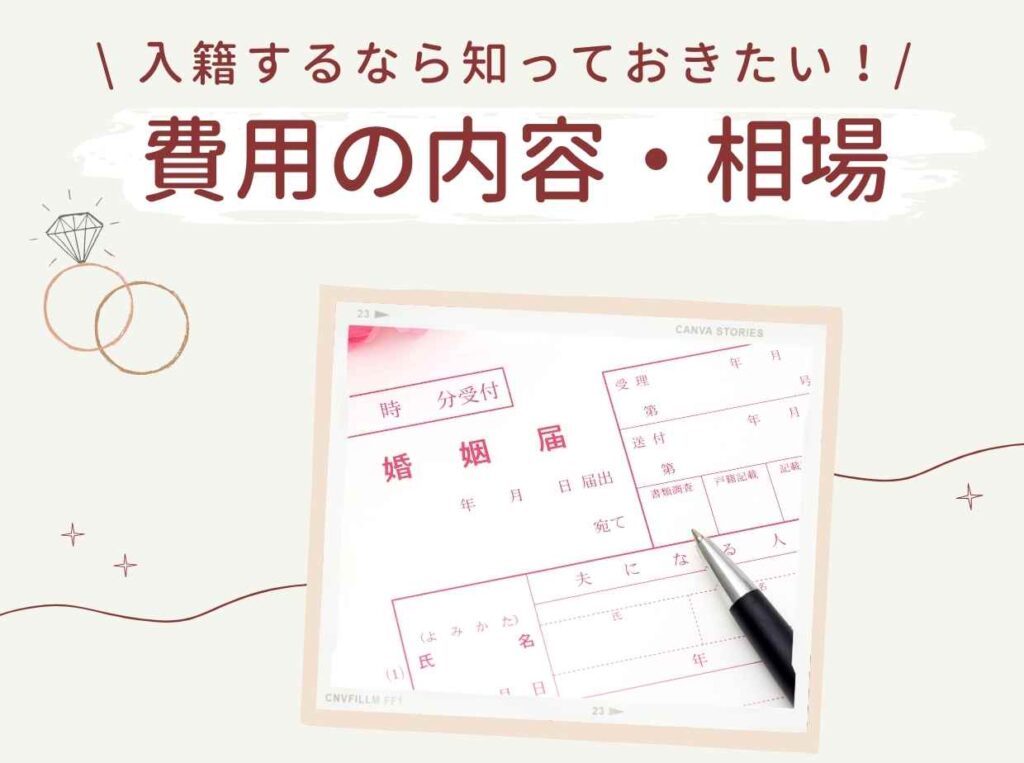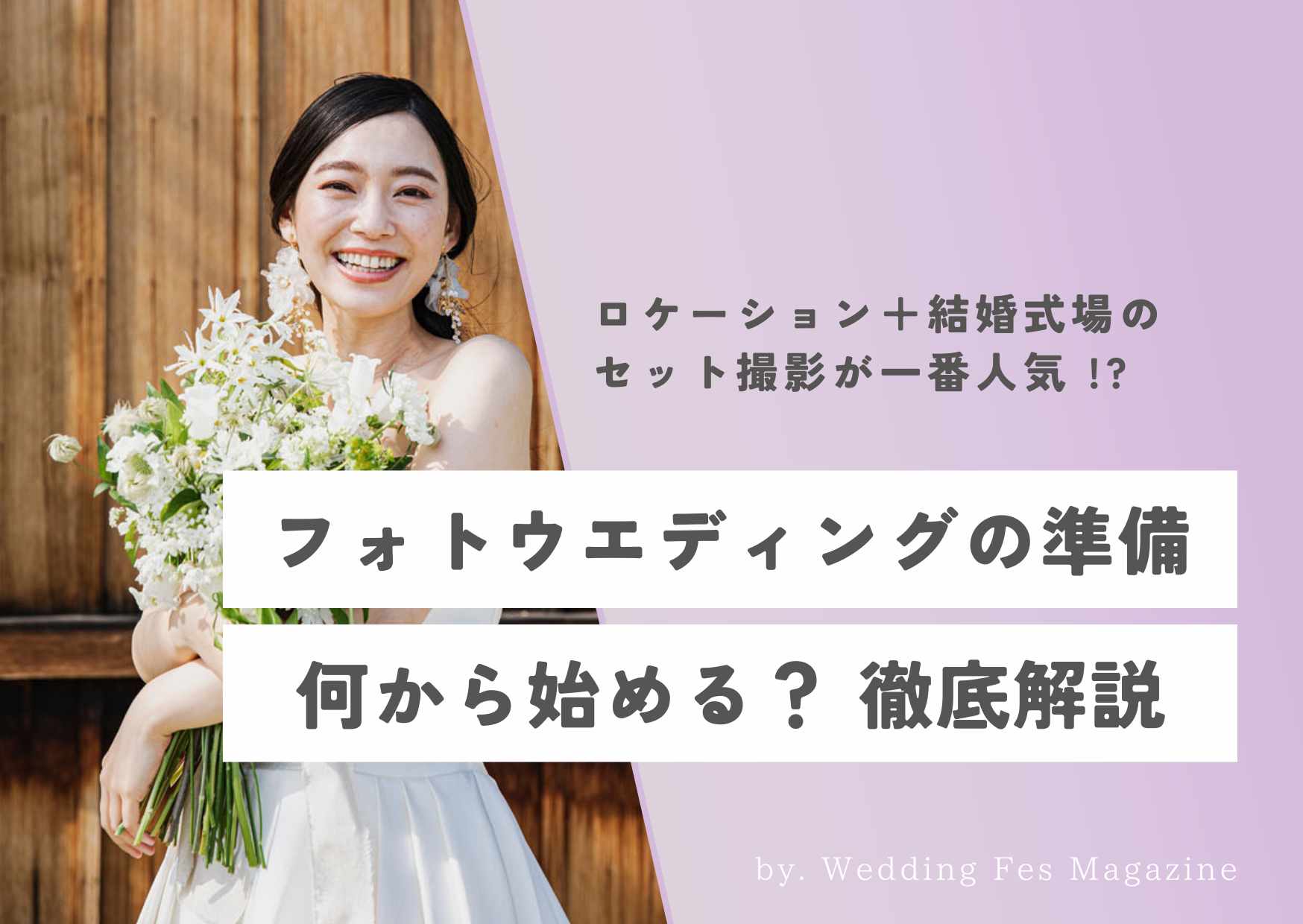結婚や入籍が決まったら、会社へ報告する必要があります。
引っ越しや両家への挨拶、結婚式の準備などで慌ただしくなるなか、会社へ報告するタイミングについて悩む人もいるのではないでしょうか。
この記事では、会社へ結婚の報告をするタイミングや、上司と同僚それぞれへ報告する際のポイントについて紹介します。

入籍が決まった!報告を会社にいつすべき?
入籍が決まった!報告を会社にいつすべき?
入籍が決まったとき、会社への報告はいつすべきなのでしょうか。
まずは、会社に報告すべき理由と最適なタイミング、また、一般的な報告の順序について紹介します。
会社に入籍の報告をする必要性とタイミング
結婚はプライベートなことではありますが、報告するのは社会人の礼儀として欠かせません。
また、入籍後の年金や保険、住所、氏名変更など、各種手続きをスムーズに済ませるためにも重要です。
結婚報告のタイミングについて、会社によっては社内規定や就業規則に明記されている場合があるので、確認しておくと安心です。
結婚を機に退職する場合は、遅くても結婚式の3ヶ月前までに報告を済ませておきましょう。
引き継ぎに時間を要するため、一定の期間を確保しておく必要があります。
また、結婚式をしない場合でも入籍日の1か月前を目安に報告します。
できるだけ入籍後の報告にならないよう、配慮しましょう。
会社への報告をしないまま、入籍後に結婚していたことが判明するような形になると、迷惑をかけてしまうことになるでしょう。
場合によっては、信頼関係が崩れてしまう可能性もあります。
結婚式をせず、入籍後に退職をしない場合でも、会社への報告は欠かさず行いましょう。
報告の順番を守ることが大切
入籍や結婚の報告を会社にするときは、職場の人間関係を混乱させないよう、「報告する相手」の順番を守ることが大切です。
伝える順番は以下の通りです。
直属の上司→直属以外の上司・人事部→同じ部署の先輩→同僚
仲の良い同僚に報告するのは、上司や先輩に伝え終わったあとが一般的です。
派遣社員の場合は、まず派遣会社の担当に伝え、現場の上司に報告するようにしてください。
会社の上司に入籍の報告をするポイント

会社の上司に入籍の報告をするポイント
会社の上司に入籍を報告する際、どのようなポイントを意識すれば良いのでしょうか。
ここからは、会社の上司に入籍や結婚の報告をする際の具体例と注意点について紹介します。
会社の上司に入籍報告をする具体例
会社の上司に入籍や結婚の報告をする場合、結婚式に上司を招待するか否かで伝え方に違いがあります。
■結婚式に上司を招待する場合
| 私事ではございますが、この度以前よりお付き合いさせていただいておりました〇〇さんという方と入籍することになりました。 結婚後も引き続き勤続させていただきたいと考えております。 結婚式の方は、〇月〇日に〇〇式場で挙げる予定です。日頃よりお世話になっている〇〇チーフに、ご出席とスピーチをお願いしたいと考えているのですが、ご都合いかがでしょうか? また、今後新婚旅行のための休暇取得や、将来的に出産、育児休暇の取得等も必要になるかと思います。ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
※上司を招待しない場合には「親族のみで挙式を行うため・・・」など、その理由について一言伝えましょう。
お詫びの言葉も添えておくと丁寧です。お祝いを頂いた際にはしっかりとお返しをして、お礼を伝えるのが良いですね。
■結婚式をあげない場合
| 私事で大変恐縮ですが、この度結婚することになりましたのでご報告させていただきます。お相手は、かねてよりお付き合いさせていただいておりました〇〇さんです。結婚後も引き続き勤務させていただく予定ですので、今後ともよろしくお願いいたします。結婚式は、相手や両家との話し合いで行わないことに決まりました。 代わりに〇月頃に新婚旅行を計画しておりまして、〇日ほど休暇をいただきたいと思っております。近づいてまいりましたら再度ご相談させていただきます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 |
結婚や入籍の報告をする際には、結婚式の有無や招待する場合にスピーチを依頼するかなど、今後の予定を伝えることが大切です。
会社の上司に入籍の報告をする際の注意点
会社の上司に入籍の報告をする際には、声をかけるタイミングに注意しなければなりません。
プライベートな話になるため、声をかけるのは就業時間外が一般的です。
「私的なことでご報告がありますので、お手隙の際にお時間をいただけませんか?」など、声をかけておくと良いでしょう。
また、スムーズに報告するため、事前に伝えるべき内容をまとめておくこともポイントです。
具体的には、以下のようなことを決めておきましょう。
- 手続きに関わること
・結婚後の働き方
・引っ越し
・住所変更の有無
- 休暇に関わること
・結婚式や新婚旅行の日程
・引っ越しの日程
・妊娠の有無 - (必要であれば)結婚式の招待について
・招待する相手
・人数
・スピーチの依頼
結婚後も勤続し続けるのか、苗字や引っ越しによる住所変更の有無など、会社で必要な手続きに関わる報告は欠かせません。
また、結婚式や新婚旅行、引っ越しの日程、現時点での妊娠の有無など、休暇取得に関わる報告も行う必要があります。
上司を結婚式に招待したい場合、結婚や入籍の報告と合わせて伝えておくと安心です。
報告の際に、結婚式に招待したい人の範囲や人数、スピーチを依頼するかなど上司のスケジュールに影響する内容についても伝えておきましょう。
職場結婚の場合には、同じタイミングでそれぞれの上司に報告するのがおすすめです。
タイミングがずれてしまうと、人づてに伝わってしまう可能性があるため注意しましょう。
後日ふたりそろってお互いの上司にも報告すると、より丁寧に結婚の報告ができます。
異動や転勤の可能性がある場合には、入籍や結婚の報告と同時に働き方の希望を明確にしておくことが大切です。
近年では、友人や知人への報告としてSNSに結婚や入籍の報告をあげることもあるでしょう。
そのような場合には、まず上司に伝えてからSNSにあげるなど、報告する順番に注意する必要があります。
また、結婚式の有無は、会社としてご祝儀を出すか、結婚式に参列する社員の休暇取得などにも関わる重要なものです。
そのため、結婚式を挙げないのであれば「両家で話し合ったうえで決定した」などのように、経緯についても説明しておくと安心です。
また、報告する際には電話やメールではなく、可能な限り直接口頭で伝えるようにしましょう。

会社の先輩・同僚に入籍の報告をするポイント
会社の先輩・同僚に入籍の報告をするポイント
ここからは、会社の先輩や同僚に入籍や結婚の報告をする際のポイントとして、具体的な文例や注意点を紹介します。
会社の先輩・同僚に入籍報告をする具体例
会社の先輩と同僚に入籍を報告する場合には、目上の先輩や距離感のある同僚と仲の良い友人関係にあたる同僚とで報告する文面を変えると良いでしょう。
■結婚式に先輩や同僚を招待する場合
| 私事ですが、〇月にかねてよりお付き合いさせていただいておりました〇〇さんという方と入籍することになりました。〇月に結婚式を予定しており、ぜひご参加いただきたいと思っております。後日、正式に招待状をお送りしますので、お忙しいところ恐縮ではございますが、ご都合がよろしければご参列ください。 また、今後は引き続き勤続予定です。新婚旅行等の休暇取得でご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 |
※招待しない場合には、「会場の都合上、人数が呼べず・・・」などその理由も一言伝えておきましょう。披露宴に呼べない代わりに、二次会に招待したり、直接報告する場を設けたりするのもおすすめです。新婚旅行で休暇を取得した際には、お土産などを用意しても良いかもしれません。
■結婚式をあげない場合
| 私事で大変恐縮ですが、今年の〇月に入籍することになりました。お相手の方は〇〇さんという方です。今後も引き続き勤務させていただきますので、よろしくお願いいたします。結婚式については、お相手の方と両家にて話し合った結果執り行わないことにいたしました。〇月頃に新婚旅行を予定しており、休暇の取得などでご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 |
会社の先輩・同僚に入籍の報告をする際の注意点
会社の先輩や同僚に入籍や結婚の報告をする際には、職場内で報告を聞いている人、聞いていない人をつくらないことが大切です。
人間関係に影響する恐れがあるため、上司に報告を済ませたあとは、なるべく早めに報告を済ませましょう。
職場内で結婚式に招待しない人がいるときは、招待しない人がいることについて、招待する人と情報を共有しておくと安心です。
また、結婚や入籍の報告をする際には、仲の良い同僚に真っ先に報告するのは避けた方が良いでしょう。
自分の口で上司や先輩に伝える前に、情報が伝わってしまうのを避けるためです。
どうしても仲の良い友達に先に報告したい場合は、ほかの人にはまだ言わないようにしてほしい旨を伝えておく必要があります。
会社で入籍の報告を行う際には、可能な限り自分の口で伝えられるように配慮することが大切です。
まとめ
入籍や結婚の報告を会社で行う場合、まず上司に伝えなければならないのは、休暇の取得や苗字、住所などの変更手続きが必要になることも理由のひとつです。
上司に最初に伝えておけば、手続きのサポートや休暇の相談もしやすくなるでしょう。
先輩や同僚に伝える場をセッティングしてもらえるなど、報告の場を設ける際にも上司が一役かってくれるかもしれません。
報告する内容を整理したうえで、実際に入籍する前には報告を済ませておくと良いでしょう。
今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!